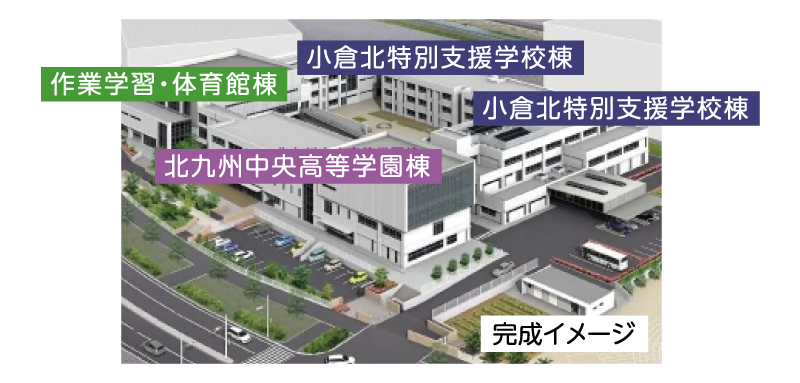特別支援教育は、障害のある子どもの自立と社会参加のために、一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援を行う教育です。
北九州市では、障害の有無にかかわらず誰もが生き生きと活躍できる共生社会の形成を目指し、多様なニーズに対応した教育・支援を行っています。
- 市の担当課
- 教育委員会特別支援教育課 電話093-582-3448
就学前
- ●保育所
- ●幼稚園 など

就学中

卒業後
- ●進学
- ●就労
- ●福祉施設 など
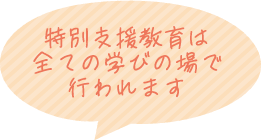
※就学相談については下記を参照
多くの職員が特別支援教育に関わっています

小倉総合
特別支援学校
村上美香さん
学校配置看護師
呼吸や栄養などの医療的ケアの実施や日常的な健康管理を行います。
一人一人の状況に応じた医療的ケアを確実に行い、子どもたちの安心・安全な学校生活を支えています。ささいな変化も見逃さないよう健康状態の把握と情報共有に努めています。

若園小学校
舩戸亜紀さん
特別支援教育コーディネーター
担任への支援、関係機関との調整、保護者の相談窓口などを担当しています。
子どもたちの実態把握やケース会議を通じて、子どもに合った支援の方法を担任の先生や外部専門家と考えます。
子どもたちの思いに寄り添った特別支援教育を学校全体で推進しています。

広徳小学校
(小倉南区担当)
原田文子さん
特別支援教室 通級担当
各区担当者が各小学校を巡回し自立支援を行います。
子どもが安心感を持ちながら自分の力を伸ばせる場、ほっとできる場であるよう心がけています。
特別支援教育学習支援員
通常の学級で授業を受けている支援が必要な子どもに付き添い、学習のフォローを行います。

若園小学校
吉岡雅子さん
分かりやすい教材を手作りすることも。子どもとの距離が近く、「何に困っているか」気付きやすいので、担任の先生と一緒に解決することができます。

広徳小学校
近津優子さん
授業中は横でヒントを与えたり、「手を挙げてみようか」と声をかけたりします。繊細な子ども、元気な子どもなど、一人一人に合わせたフォローを心がけています。

鳴水小学校
梅木佳菜さん
特別支援教育介助員
肢体不自由等のある子どもに付き添い、移動介助や学習中の身体補助などを行います。
介助するお子さんだけでなく、担任の先生や他の子どもたちとのコミュニケーションも大事にしています。子どもたちができた喜びを味わえるようサポートしています。
昨年8月に小倉総合特別支援学校を訪問した際、授業や給食など、安全確保に努めながら子どもたちに寄り添い、一つ一つ丁寧に対応する職員の姿や、楽しそうに過ごす子どもたちの姿が印象的でした。
現在、発達障害や難病を含めると日本人の10人に1人は障害があるといわれています。障害に限らず、人はそれぞれ、さまざまな個性や差がある人同士、共に生きるのがこの世の中です。「与える人」「与えられる人」に分かれるのではなく、互いに必要な時には支え合える「共生社会」を目指します。
特別支援教育もその一つです。子どもたち一人一人がそれぞれの形で自立と社会参加していける、そんな北九州市を市民みんなの力でつくっていきましょう。
北九州市長 武内 和久

▲小倉総合特別支援学校の調理員の皆さんと

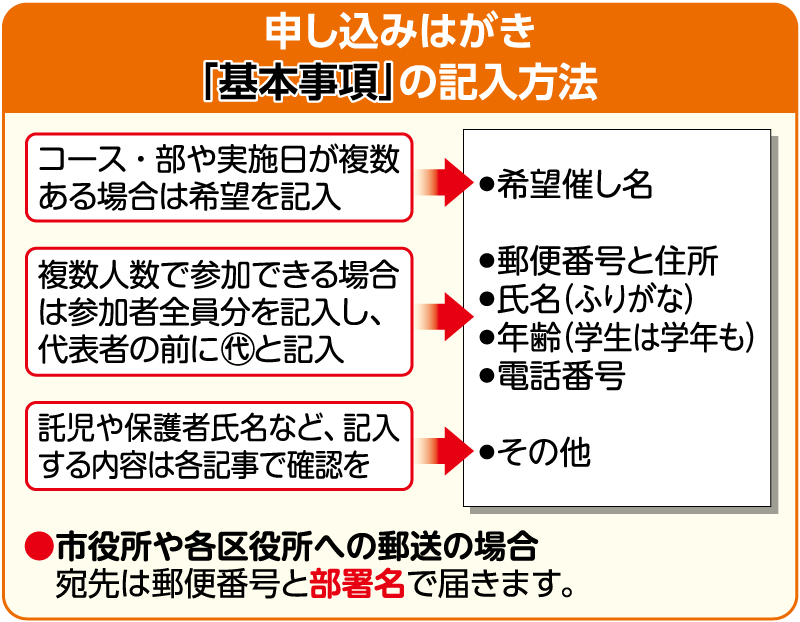
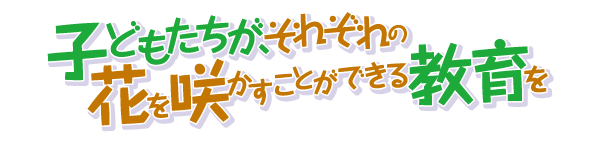

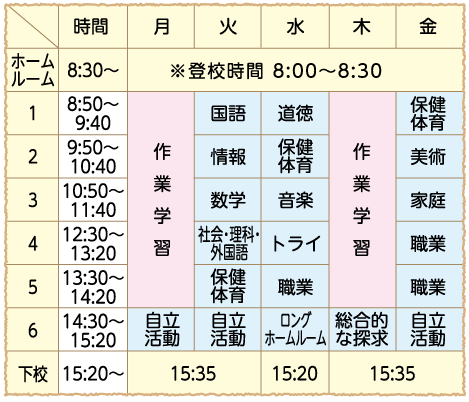




 パン・接遇班
パン・接遇班
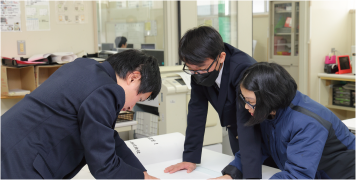 事務・軽作業班
事務・軽作業班
 清掃・福祉班
清掃・福祉班
 農耕班
農耕班