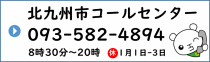計量法では、さまざまなマークが定められています。
皆さんの身の回りにもこのマークがついた計量器がたくさんありますので、
ぜひ探してみてください。
計量に関するマーク
検定証印

はかりや電気・ガス・水道メーター等について、製造時(計量器によっては有効期間ごと)に都道府県知事⼜は指定検定機関(電気計器は⽇本電気計器検定所)が検定を行い合格したものにつけるマークです。
取引証明に使う計量器は必ず検定証印等が付いたものでなければなりません。
基準適合証印

指定製造事業者が製造した計量器が、⾃主検査において型式承認を受けている範囲で技術基準に適合している場合、その計量器に表示することができるマークです。
「検定証印」と同じ効力をもっています。
家庭用計量器

家庭で使用する一般用体重計(ひょう量注)が20kgを超え200kg以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの)、乳幼児用体重計(ひょう量が20kg以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重を計量するもの)、 調理用はかり(ひょう量が3kg以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量を計量するもの)が計量法に定める技術基準に適合していることを表すマークです。
家庭用計量器は取引及び証明には使用できません。
注)ひょう量:計ることができる最大の質量。
適正計量管理事業所

工場やデパート・スーパーなど特定計量器を使⽤する事業所のうち、適正な計量管理を行っているものとして都道府県知事に指定された事業所が掲げることができるマークです。
定期検査済証印

取引・証明に用いる特定計量器のうち、検定の対象となる非自動はかり、分銅・おもり、皮革面積計について、定期検査を受け合格したことを証明する印です。このシールを合格した計量器に貼付します。
特殊容器

特殊容器とは、体積を計量する代わりに、ある高さまで液体商品を満たした場合、正しい量が確保されるように製造された、透明又は半透明の容器(例えば、ビールびん、醤油びん、牛乳びんなど)のことです。俗に「丸正びん」と呼ばれます。
このマークがついた特殊容器は、経済産業大臣から指定を受けた者(指定製造者)が製造し、かつ計量法の規定に適合するものであることを表します。
このページの作成者
総務市民局安全・安心推進部消費生活センター計量検査所
〒803-0805 北九州市小倉北区親和町6番2号
電話:093-592-2012 FAX:093-562-7803
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。