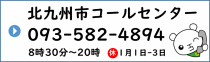令和7年2月12日(水曜日)14時00分から16時00分まで
第58回北九州市環境影響評価審査会議事要旨(令和7年2月12日)
1 日時
2 開催方式
ウェブ会議
3 出席者
委員
伊藤委員、岩松委員、岡本委員、川﨑委員、北沢委員、楠田会長、柴田委員、副島委員、田中委員、豊貞委員、中西委員、三笠委員、蓑島委員、村瀬委員
事業者等
北九州市(都市戦略局都市交通政策課)[都市計画決定権者]、山口県[都市計画決定権者]、国土交通省中国地方整備局、国土交通省九州地方整備局、福岡県、下関市
事務局
環境局環境監視部環境監視課(環境監視部長ほか4名)
4 議題
「下関北九州道路に係る環境影響評価準備書」の審査
5 議事要旨
(楠田会長)
それでは審議に入らせていただきます。まず事前に頂戴しています委員の皆様方からのご意見につきましては、委員にご発言をいただいて、事業者から回答を頂戴することにいたします。それではまずは、今日は欠席されている藍川委員から大気質に関する質問を頂戴しております。事務局の方でお読みいただけますでしょうか。
(事務局)
はい。事務局から代読いたします。
まず準備書12-2についてです。予測結果の欄で記載文と表中の数値の整合性を確認してほしいというところです。具体的には、評価結果の2行目から3行目に二酸化窒素の日平均値の結果を示していますが、最大の値が、記載文中は0.03541ppm、表中は最大のものが0.03550ppmというのがありますので、その確認をお願いします。
もう1点、準備書12-2、同じところの環境保全措置及び事後調査についてです。「予測手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査を行わないものとします。」について、移流・拡散計算については、ある程度は確からしいと考えることに一定程度の妥当性があるのが考えられる。一方、交通量予測に基づく、大気汚染物質発生量には、想定外の渋滞発生等の不確実性が存在することを懸念する。ついては、現地測定事後調査は行わないまでも、「環境要因の区分」が土地または工作物の存在及び供用(自動車の走行)であることから、大気汚染防止法に基づく地方自治体の観測結果(常時監視結果)を注視・確認する等の事後フォローが必要なのではないか。以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは、ただいまの藍川先生の意見につきまして、事業者から回答を頂戴いたします。よろしくお願いします。
(事業者)
はい。二つのご意見について、まず一つ目でございます。表中の数字の整合性ということでございますが、大変申し訳ございません。こちら誤りでございます。評価書の段階で修正させていただきます。これが一つ目の回答です。
二つ目のところでございますが、ご意見は、観測結果等を注視確認する等の事後のフォローが必要ではないのかということでございます。こちらの事業者の回答は、準備書の第12章に記載してあるとおり、事業実施段階、供用後において、周辺の交通ネットワーク等に関する交通量や生活環境の状況の変化について、関係機関と協力し、必要に応じて適切に把握して参ります。その結果、現段階で予測しなかった著しい影響というものが見られた場合には、環境に及ぼす影響について調査し、専門家の意見を踏まえながら、最新の技術指針を踏まえて、適切な措置を講じて参りますということでございます。以上になります。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは続きまして、ご出席の川﨑委員から意見を頂戴しています。川﨑委員、ご発言いただけますでしょうか。
(川﨑委員)
それでは私の意見ですが、秋のヒヨドリの渡りについてでございます。下関市彦島にある関門都市霊園というところがありまして、ちょうど海に面したところで、その周辺からヒヨドリが飛び出しまして、受け入れ側として小倉北区の西港から赤坂海岸に至る間を渡っているという状況です。この渡りの方向については、風向きなどによる気象条件によって変わり、北風が強いとどうしても押されて赤坂の方に流れるような形になるのですが、多くは西港から小倉港がメインコースになっておるところです。この関門海峡を渡るヒヨドリを狙って、彦島側にいるハヤブサが、ヒヨドリが飛び出した後、遅れて飛び出して、海峡の中央付近で襲うパターンが一般的であります。しかし、橋ができますと、ちょうど橋が渡りのコースに沿うような形にできますので、橋の中央付近の橋脚に留まって、下を渡るヒヨドリを襲うことで省力かつ効率的な狩りが可能となり、襲撃のパターンがこのような形に変わる可能性が高いと考えられます。そうなると、ヒヨドリも橋からのハヤブサの襲撃を嫌って、赤坂海岸の方向に渡るコースがメインになる可能性が考えられます。現在の移動コースは、西港-小倉港間に上陸した群れが、戸畑区の金毘羅山を経由して大蔵方向に向かい、その後、皿倉山に至るといったコースなのですが、赤坂海岸に上陸したヒヨドリは、足立山方向に向かい、その後の移動コースについては、どういったコースをたどっているのかというのがあまり知られておりません。つまり、橋ができた影響で、ヒヨドリの生態に大きく影響する可能性があると考えられるので、足立山に向かった群れがどのコースをたどっていくのかを確認しておくべきではないのかということでこの質問を出しました。以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは、事業者から回答いただけますでしょうか。
(事業者)
秋のヒヨドリの渡りについてということで、回答ですが、まず、ヒヨドリの渡りの調査、予測、評価につきましては、道路環境影響評価の技術手法を参考に専門家の助言を得ながら行っているところでございます。秋季のヒヨドリの渡りの現地調査の結果については、準備書の第11章の11-9-31ページに記載をしているとおり、事業実施区域及びその周辺においての飛翔ルートというところを確認をしております。その飛翔のルートを踏まえた予測の結果でございますが、基本的にヒヨドリの主要な渡りの経路である海域を橋梁構造で通過をいたしますけども、現状のルートを踏まえれば、ヒヨドリの移動経路というものは確保されるということで予測をしてございます。ただし、川﨑委員のご意見のとおり、飛翔ルートの変更については、基本的な生態等もまだ不明であり、わかっていないところもございます。事業実施段階及び供用後において、このような自然環境の状況の変化等については、関係機関と協力し、必要に応じて適正に把握して参りたいと思っているところです。また、現時点で予測し得なかった著しい影響、情報が得られた場合には、改めて調査をして、専門家のご意見を踏まえながら、技術指針に基づいて必要な措置を講じていきたいと考えておるところでございます。以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。川﨑委員、追加のご発言ございますでしょうか。
(川﨑委員)
渡りのコース自体は確保されていますが、供用が始まった後、そういった生態が変わってくるということがあり、渡りのコースが変わってくるというのは、この段階では、影響が大きいのかわからないところですが、渡りのコースに影響が生じた時には、検討していただければと思います。コースが変わったからといって、ヒヨドリ自体が死んでしまうというわけではないので、なかなか難しいところではございますが、生態が変わるっていうことを確認、把握して、こういうこともあり得るんだということを覚えていていただければと思います。以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。事業者から何か追加のご発言ございますか。
(事業者)
委員のご指摘のとおりかとは思います。我々の方も専門家の助言を得ながら、これまで調査、予測、評価をしてきたところでございます。この橋梁ができると、どのようなコースになるのかというところについては、まだまだ知見がない状況でございます。ですので、状況が変わるということも頭の中に想定しながら、著しい影響が見られた場合には、専門家にまたご相談を差し上げ、そして保全措置を検討していきたいと考えているところでございます。ありがとうございました。
(楠田会長)
川﨑委員よろしいでしょうか。
(川﨑委員)
はい。了解しました。
(楠田会長)
ありがとうございました。それでは続きまして、ご意見を頂戴している蓑島委員からご意見を改めて頂戴できますでしょうか。よろしくお願いいたします。
(蓑島委員)
準備書11-9-64のナガマルチビゲンゴロウを偶発的と判断されていますが、その根拠をもう少し詳しく知りたいと思います。過去の採集事例を見ると、植物がないようなところにもいるという例もあるので、福岡県側は厳しいかもしれないですが、山口県側だったら、もしかしたら何か水たまりがあって、そこにいる可能性もあると考えられます。今回、山口県側は考慮に入れないということなので、山口県側で採れていれば、いるのではないのかという提案をするぐらいです。福岡県側で採れている場合は、注意が必要なのではないかと思いましたので、根拠をお教えいただければと思います。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは、事業者から回答を頂戴いたします。よろしくお願いします。
(事業者)
[注)ナガマルチビゲンゴロウの生息状況についての発言のため、希少種保護の観点から非公開とします。]
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは蓑島委員、よろしいでしょうか。
(蓑島委員)
はい。ありがとうございます。
(楠田会長)
それでは続きまして、副島委員から事前にいただきましたご意見のご説明をお願いいたします。
(副島委員)
はい。今回、重要植物の出現位置についてということで質問させてもらったのですが、この件に関しまして、ハマハナヤスリの生育地域に関しての情報を個別にいただきました。このハマハナヤスリという植物、少し放浪性があるというのか、あちこちに出現しては消えるというような性質があるかと思います。これに関しては、1地点1個体しか確認できていないということなのですが、例えばこの1個体が消えてしまった場合にはどうなるのかというようなことの予測はできないでしょうか。要するに域外での調査というのは全くされてないということなのでしょうか。そこをお伺いしたいと思います。
(楠田会長)
はい。承知いたしました。それでは事業者から回答を頂戴いたします。お願いします。
(事業者)
今のご意見について、改めて確認をさせていただきます。事前の情報を提供した際には、ハマハナヤスリというのが、北九州市側で一つ確認がされているということでございます。この地域については、本事業での改変はないということで、我々は予測の結果、保全されるとしておりますが、ご意見は、このハマハナヤスリがなくなった場合はどうするのかということですか。
(副島委員)
どうするのかというよりは、1個体しか見つかってないということなのですが、それ以外の地域には全くないのかどうかというのが気になります。
(事業者)
まず、我々事業実施区域からプラス両端100メートルの範囲で調査をさせていただいています。その事業実施区域というものも、方法書の段階では1キロ幅を設けておりまして、そこからプラス100メートルの範囲で調査をさせていただいているというところでございます。その結果からハマハナヤスリというもの自体は、この事業実施区域及び周辺では、ここ1件だけしか見つからなかったということでございます。
(副島委員)
でもそれでも影響はないということなのですね。
(事業者)
ですね。改変もないということですので影響はないと予測をしているところでございます。
(副島委員)
はい。わかりました。それ以外、事後調査やモニタリングの話が植物に関わらず、先ほどのご説明でもたくさん出たのですが、例えば工事の実施中に何かしらの大きな影響が認められた時というのは、その工事の中断をして、その影響を見定める、あるいは、中断によってその影響がどう変わるのかというのを見定めたりは考えられるのでしょうか。
(事務局)
はい。例えばですね、事後調査を行いまして、猛禽類等についての影響がある、ここで保全措置が必要だというような判断された場合には、工事を一時中断して速やかに専門家にご意見を伺います。その結果をもって、措置を講じて、また工事を再開するということを考えているところでございます。
(副島委員)
わかりました。ありがとうございます。私の方から以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは、次に村瀬委員からご発言を頂戴いたします。
(村瀬委員)
はい。まず表についてです。準備書11-10-39の表の植物相(水生生物)の備考欄には「北九州市域あるいは下関市域」と記されていますが、同じ表の付着生物(植物)と植物プランクトンの備考のところは「-」で示されているということになって、これは何を示すのかというところと、これらの調査は、両市で実施したと推察しますが、この場合は「-」ではなく、わかるようにどちらの市なのか、あるいは両市なのかということを記す必要があるのではないかという質問です。
続けて、準備書11-10-40以降の表と、数でページ言うと準備書11-11-20以降の表について、調査結果として出現した場所がわかる場合には、北九州市側なのか下関市側なのか、あるいは両方の市なのかというのを追記することが必要であるというところです。まずこの2点について確認したいと思います。
(事業者)
はい。ありがとうございます。それではただいまのご質問につきまして、事業者から回答を頂戴いたします。よろしくお願いします。
(事業者)
「北九州市側」「下関市側」というような記載がある一方で「-」になっているということも含めて、おそらく二つの回答が同様な回答になると思います。基本的に海域というところについては市境がないということなので、どこで確認されたかという情報はわかっていますが、それが「北九州市側」「下関側」という表現ができないので「-」としてございます。ただ、出現確認した場所につきましては、準備書の確認位置図で示させていただいているところでございます。以上になります。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。よろしいでしょうか、村瀬先生。
(村瀬委員)
はい。承知しました。続けて、ページ数で言いますと、準備書11-10-63から65の表のところで、アツバノリとアマモを重要な種として挙げていますが、事後調査は行わないとしています。一方、北九州市ではゼロカーボンシティ宣言を表明し、最近ではブルーカーボン生態系の一つである藻場による二酸化炭素吸収源に着目して、港湾で藻場造成などの取組が行われています。このような市の取組に鑑みて、北九州市側の事業実施区域とその周辺の護岸や消波ブロックに生育している多様な海藻類は二酸化炭素吸収に寄与していると考えられます。これらのことから、本事業の実施区域と近隣の護岸や消波ブロック上の海藻類、下関側ではアマモ場を加えるというところと、及びレッドデータ対象のアツバノリについては、出現する海藻類の分布面積、被度及び現存量などを把握する必要があると思うのですが、こういったことは事後調査で検討していないのかということをお伺いしたいと思います。
また、続けて準備書11-11-38から73の各表には、イソガニ類、スナメリ、スズキ、マダイ、マダコ、マハゼ、メバル、アサリ、こういった生態系の注目種を予測結果として示していますが、スナメリ以外は事後調査の対象にはなっていません。これらの種は、水産的に重要な種であり、工事中には汚濁防止膜により水の濁りが抑制されるとは書いてありますが、関門海峡の潮流の緩急や転流、それから風向き、船舶の航行などにより複雑化するため、水の濁りによる水産有用種への影響を事後評価で検討する必要があるのではないかと考えています。特にマダコ、マハゼ、アサリは水の濁りだけではなくて、海底に生息する動物類なので、海底の浮泥の堆積というのが懸念されます。こういうところから濁りと浮泥の堆積などの影響を把握することを事後調査で検討してはいかがかというところです。まずここまでお伺いしたいと思います。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは、事業者から回答を頂戴いたします。お願いします。
(事業者)
一つ目の藻場、アツバノリ、アマモに関してでございますが、こちらの調査をし、今の情報をもって予測、評価をしてございます。その結果、生育環境が保全されると予測をしております。その上で、事後調査につきましては、環境影響評価法ないしは国土交通省令で言われている事後調査というものは、基本的には予測の不確実性がある、ないしは、効果の不確実性がある等々の場面において行うとされております。この環境影響評価法、省令に基づいて我々が検討した結果、事後調査というものは行わないこととしてございます。ただ、このような重要なものについて、現時点で予測し得なかった著しい影響が見られた、また、環境の変化に応じて影響が顕著に見られるというような場合においては、環境影響について調査をして、そして最新の技術指針、更には、最近はブルーカーボンと言われております国の環境政策がこの時点でどういう状況かということも含めて、必要な措置というのはその時点で考えていきたいということでございます。これが一つ目の回答になります。
そして二つ目の水産的な有用な種についてでございますが、こちらの汚濁防止膜の効果については、「港湾工事における濁りの影響予測の手引き」が国土交通省で策定され、この手引きをもとに、蓄積されたものとして、その効果を含めて、予測、評価をしているところでございます。その汚濁防止膜の具体的な検討時期というのは、詳細な施工段階で検討していきますが、それも最新の技術指針等を踏まえて決定していきたいと思ってございます。そして、事後調査につきましては、先ほども言っているとおり、技術手法等によって、予測の不確実性、更には、採用した保全措置の効果の不確実性を省令の考え方に沿って検討した結果、事後調査は行わないこととしているところでございます。浮泥についてのご指摘もございます。こちらも「港湾工事における濁りの影響予測の手引き」によれば、港湾工事に伴う浮泥の環境影響について報告された例はなく、一般的には問題になっていないものとして考えております。ただし、現時点で予測しなかった著しい影響が見られた場合には、影響について調査をして、専門家のご意見を聞きながら、必要な措置というものを講じて参りたいと考えております。以上になります。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。村瀬委員よろしいでしょうか。
(村瀬委員)
著しい影響があった場合には、対応するという理解でよろしいということですかね。
(事業者)
はい。そのような場合には、専門家のご意見を聞いて、必要な措置というのは講じていきたいと考えております。
(村瀬委員)
はい。承知しました。最後にスナメリのところですが、これは事後調査を行うということになっていますが、情報として二つほど文献を挙げましたが、昼と夜、生息状況の違い、あるいは単独性なのか群れを作ってるのかっていうのを事後調査で検討していただきたいという希望があります。また、準備書11-11-74のところに、調査海域を橋脚周辺と書いてありますが、周辺というのは、橋脚からの距離としては具体的にどれぐらいの範囲なのかというのをお聞きしたいと思います。以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは事業者の方からお願いします。
(事業者)
スナメリの事後調査は行っていくと準備書には書いてございます。その範囲でございますが、基本的には事業実施段階で、これから専門家のご意見をお聞きしながら、検討はしていきたいと考えてございます。スナメリの移動能力、そして行動範囲もあります。そういった点を踏まえて、調査の地域というところは考えていきたいと思いますが、ただ、影響の範囲というものにつきましては、橋脚の掘削工事に伴っての水中音が影響を及ぼすと予測をしているところでございます。ですので、基本は、橋脚の周辺で、どの程度まで広げるかは、専門家のご意見を聞きながら、今後、事業実施段階で検討していきたいと考えてございます。また、夜間と昼間との特性の違い等々につきましては、我々もこの準備書を作る上では、スナメリの専門家にご相談を差し上げ、事後調査はどうあるべきかということもご意見を踏まえて、決めてきているところでございます。そのために、調査方法としては、準備書で書いてあるとおり、トランセクト法また定点観測法、これだけではなく、水中の音響解析によっての生息状況の確認、水中音の調査、諸々含めて、特性も把握しながら考えていきたいと思っているところでございます。以上になります。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。村瀬先生よろしいでしょうか。
(村瀬委員)
はい。スナメリの専門家の先生に聞きながら事後調査を進めていくというところで理解しました。どうもありがとうございます。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは次のご質問は、今日出席されています委員の皆様方から頂戴いたします。どうぞご意見がございましたら、リアクションの中にあります挙手ボタンを押していただければ幸いです。それでは、岡本委員お願いいたします。
(岡本委員)
岡本です。騒音の予測について意見ですが、まず準備書で、事後の調査を行わないとされていますが、実際には、施工状況や排水性舗装の目詰まりといった経年変化の影響などで環境基準の数値を超えることも考えられますので、例えば常時監視の地点に加えていただくなど、事後の確認や問題が生じた時の対応を検討していただきたいと考えています。
追加で、評価書の方でご検討いただきたいのですが、予測に用いられているASJ RTN Modelについては、最新版がありますので、そちらを参照していただきたいということと、環境保全措置について、遮音壁以外の対策については、準備書では予測方法の詳細を確認できませんでしたので、評価書の段階では可能な範囲で、根拠となる情報を示していただきたいと考えています。以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは、事業者からの回答を頂戴いたします。
(事業者)
はい。3点ございました。まず一つ目です。排水性舗装等の目詰まりのデメリットもあるのでしっかり監視をし、環境基準の維持に努めてもらいたいというようなご意見だと思います。環境の変化については、工事中また供用後についても、関係機関と協力して適切に把握していきたいと思っております。その中で騒音規制法等による監視結果等も収集しながら状況を確認し、そこで影響がまた改めて顕著であるという場合には、舗装の打ち替え等も含めて、随時対応していきたいというのが一つ目の回答になります。
二つ目のASJ Modelにつきましては、令和5年3月末の情報で調査、予測、評価をしているところでございますが、つい先日、ASJ Modelの2023が公表されたのも存じております。このような手法によって、どのような影響があるのかというところについては、分析を行いながら、今後、事業実施段階でまた新たな手法が出る可能性もございます。そのことも含めて、基準の変更、モデルの変更も把握しながら、事業実施段階で対応して参りたいと考えております。これが二つ目です。
三つ目については、遮音壁の設置の範囲等はわかるけども、排水性舗装、裏面吸音盤等の設置の範囲がわからず、妥当性が不明であるというご意見だとは思います。遮音壁につきましては、基本的にどこからどこまでの必要かというところを予測検討において示しております。排水性舗装、裏面吸音板につきましては、広範囲にわたる必要性も考えられますので、今後、環境基準を達成するという前提の中での範囲を事業実施段階で決めていきたいということで、この準備書の中では示しておりません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。岡本先生よろしいでしょうか。
(岡本委員)
はい。引き続きよろしくお願いします。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは次のご質問を頂戴いたします。伊藤先生お願いします。
(伊藤委員)
二つありまして、一つは、参考までにお伺いしたいということで、現段階では予測は難しいとは思いますが、橋脚が関門海峡に建っていますが、これによって海流が微妙に変化するということがもしあるとすれば、よく護岸工事で、数キロ離れた砂浜が浸食されるというようなことをいくつか私も見たことがありますが、そういった可能性があるのかということについて、ご意見をお伺いしたいというのが1点。
もう一つは、この橋脚ができて、橋梁ができる頃というのは、多分20年とかもっと先かもしれませんが、例えば電気自動車が増えた時に、排気ガスについてはよい方向にいくと思いますが、車体重量が重くなって、路面の粉じんなど、そういったところが増えるなど、いわゆる将来車両が変わることによる影響というのをどのように考えておられるか、ご意見をお伺いしたいということです。
(楠田会長)
はい。それでは事業者から説明頂戴いたします。
(事業者)
一つ目の橋脚が設置されて、周辺の堆積物によって変わるかもしれないという可能性の話でございますが、今後事業を進めていくにあたっては、海底のボーリングをしたりして詳細設計をして参ります。その段階で、海底がどのような状況なのかということを把握しながら設計に努めていきたいと思っています。可能性までは回答はできませんが、基本的にはその状況を把握した中で、安全に、そして安心に施工ができる方法を検討していきたいというところが回答になります。これが一つ目でございます。
そして二つ目で、電気自動車等によって排ガスは緩和されるかもしれませんが、重量によって、粉じん等が膨れる可能性があるということをでございます。おそらくこのような知見が高まれば、道路環境影響評価の技術手法のパラメータ等も変わるとうに思います。その時点で、基準が変わる、そしてパラメータや手法が変わるということになりますので、そのような状況を適切に把握して、そして最新の手法をもって検証していきたいと考えております。以上になります。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。伊藤先生よろしいでしょうか。
(伊藤委員)
はい。結構です。よろしくお願いします。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは田中先生お願いいたします。
(田中委員)
廃棄物のところで3点ご質問させていただきます。1点目は、建設発生土の利用について、容量が書かれていますが、これは全体の盛土の中の何%になるのかというのが1点目の質問になります。
それから2点目は、建設汚泥についても、盛土としてできるだけ使いたいというようなご回答になっていると思いますが、その場合、脱水だけじゃなくて何か積極的に使えるような処理をされて、使われるのかというところです。建設発生土の使用量も少ない割には、汚泥のような少し厄介なものも使うと書かれています。それが本当に可能なのかというのが2点目になります。
あと3点目ですが、コンクリート殻やアスファルトなどのリサイクルをできるだけするということなのですが、それもすべてリサイクル施設、資源化施設に持っていくことで対応するというような文章になっていると思いますが、そういうリサイクル施設に持っていったとしても、誰かが使ってくれないと、そこに行って、そのあとどこに行っているかわからない状態になってしまうので、今回の工事の中で積極的にリサイクル品を使われる予定っていうのはあるのですかということ。それが3点目です。以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは、事業者から回答を頂戴いたします。お願いします。
(事業者)
一つ目の盛土、今の発生土の中で、盛土が何%かというのは、今発生量を91万9000立方メートル発生するとしていて、そのうち事業地内では13万2000立方メートル活用しますと言っている13万2000立方メートルというものは、すべての盛土プラス埋戻しも含めて使えるところには使っていきたいということになっております。なので、基本的には盛土材として利用できるものはすべて利用していきたいというところを考えている再利用量になります。
そして、汚泥につきましては、脱水処理以外にいろんな方法があるのではないかということで、今の段階ではできる限り脱水をして減量化をして、その土を他事業で再利用してもらうということを考えてございます。そのために再資源化施設に持っていくということでございます。ですので、そのほか脱水処理以外に何かよい方法があるのであれば、またその時点での技術指針や施策を踏まえて、検討はしていきたいと思っているところでございます。
そして、コンクリート、アスコンを含めてリサイクル品を活用することを考えているのかということでございますが、道路行政としては、地球温暖化に対する対策については、国土交通本省も含めて、いろんな方向性を今政策として出しております。その中でも、できる限り再資源化品を使うという方向に動いておりますので、我々も事業者としては使えるものはリサイクル品を使っていきたいという方向で対応して参りたいと考えているところです。以上になります。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。田中委員、よろしいでしょうか。
(田中委員)
2点目についてのご回答ですが、実施区域内の盛土として使うというように書いてありますが、今のご回答だと、他の事業のところにお任せするというご回答ということですか。
(事業者)
はい。基本的には切土から発生する土が、盛土材で利用するものより多いので、切土材で発生するものを盛土材で使おうとしております。その中で、汚泥というものは海域から出るもの等々ありますが、そういうものについては、そこをないがしろにせずに脱水処理を行って再利用できる形で再資源化施設に持っていきたいと考えているところです。
(田中委員)
ということは、準備書に書かれている実施区域内で盛土材というのは、ここの実施区域ではなくて、他所のという考え方ですよね。この準備書の中には、実施区域内での盛土で使うというように書いてあったので、使われるのかと。私も発生土だけでも十分あるのに、汚泥を使えるのかと疑問を持ったので、二つ目の質問させていただきました。はい。以上です。
(事業者)
汚泥については、場内で脱水処理をして減量化を図ることですね、そして事業実施区域内の盛土材として利用できるのであれば、利用していきたいということも基本的には考えておりますが、切土で発生する土の方が多いので、今の段階の13万2000立方メートルというのは、そちらを利用するとしておりますが、詳細は、詳細工事計画を立てる段階で、このような減量化によって汚泥が使えるものがあるのであれば、使っていきたいと考えているところです。
(田中委員)
わかりました。はい。以上です。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは続きまして、川﨑委員、お願いいたします。
(川﨑委員)
下関側のことなので本来はあまり言わないほうがいいかもわかりませんが、フクロウの繁殖地が2ヶ所あって、影響を及ぼすのではないかということで、対策をいろいろ出されているのですが、その中で巣箱というのが一つあります。巣箱設置は、フクロウの保護のためには、結構効果ある対策ではあるのですが、毎年、中の巣材の撤去をしないとだんだん虫が発生したりということで、だんだん使わなくなりますので、そのあたりの何かアフターフォローを巣箱の場合は、毎年やっていかないといけないというのがあります。ですから、そういったところを施工者がするという方法もありますが、地元の学校などとタイアップして、学校の環境教育の一環として、フクロウを保護するといった形で巣箱を活用するというのは一つの方策としてはあるのかと思いますので、そこについての事業者側の考えについてお聞きしたいと思います。お願いします。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは、事業者から回答を頂戴いたします。お願いします。
(事業者)
フクロウの巣箱設置については、詳細は施工計画の段階で専門家のご意見を聞きながら、どのように設置するのか、どこにするのか、そして、今のような維持管理、メンテナンスも含めてどうするのかということは決めていきたいと思っています。この巣箱設置自体が事後調査の一つになっておりますので、調査をした結果は、また事後調査手続によって、公表していきたいと考えております。この巣箱設置の目的の一つに、工事の段階で営巣地を変更する可能性があるというところで、できる限り工事から離れたところに誘導していきたいということも含めて、巣箱設置としております。代替地というよりかは、誘導というような目的もございます。ですので、そういうようなことも含めて、専門家のご意見を聞きながら、詳細は検討していきます。環境学習については、ご意見をお伺いしておきます。いろんな生態系保護もございます、事業者としての責務もございます、そのあたりについては、また今後、検討して参りたいと考えております。以上です。
(川﨑委員)
はい。了解しました。よろしくお願いいたします。
(楠田会長)
はい。ありがとうございます。それでは次のご発言頂戴いたします。どうぞ挙手ボタンを押しくださいませ。よろしいでしょうか。
それではご発言がございませんので、これで下関北九州道路に係る環境影響評価準備書の審査を終了させていただいてよろしいでしょうか。はい。それではご了解をいただきましたので、これで審査を終了させていただきます。
このページの作成者
環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。