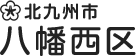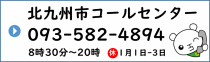長崎街道の宿場町として今も貴重な史跡や町並みが残る木屋瀬地区において、「筑前木屋瀬祇園祭」が開催されます。
筑前木屋瀬祇園祭
歴史ある「木屋瀬祇園山笠」は、本町六町の赤山笠と新町七町の青山笠の2台の山笠が町中を練り回った後、勢い太鼓の響きに合わせて境内に走り込みます。これを初日は「奉納」、2日目は「宮入り」といい、この祭りの最大の見せ場です。また、長崎街道を2台の山笠が駆け抜ける「追山」も見るものを圧倒する勢いがあります。

筑前木屋瀬祇園祭の様子
日時
令和7年7月12日(土曜日)13時から21時
7月13日(日曜日)9時30分から22時
場所
須賀神社(北九州市八幡西区木屋瀬三丁目19番1号)
交通
筑豊電鉄「木屋瀬」下車、徒歩5分
木屋瀬祇園(概要)
須賀神社の祭礼に奉仕する氏子の山笠行事です。昔は獅子頭を先頭に神輿、山笠などがならんで地域内を回る御神幸本来の形式をとっていましたが、現在では2台の山笠が町を運行する形になっています。
祭り初日の夕方、一番山、二番山(順番は隔年交替)が並んで須賀神社に入り、お払いを受けます。それが済むと山笠はそのままにして勢子だけが各々提灯を持って近くの遠賀河畔にお汐井とりに行きます。その後、リーダー(掛け合い)2人の指示で町中を練りまわります。
祇園囃子は太鼓だけです。
昔の山笠は、9メートル以上もある「岩山」(はりぼての岩を高く積み上げ、人形を飾る形式の山)であったが、大正初期の電線架設以来、4メートル程の現在の人形飾山(曳山)に変化しました。
お問い合わせ
筑前木屋瀬祇園祭実行委員会 (電話093-617-2321 須賀神社内)
このページの作成者
八幡西区役所コミュニティ支援課
〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ5階
電話:093-642-1337
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。