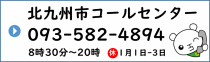ハラスメントとは広い定義で言うと「様々な場面においての嫌がらせやいじめ」のことです。
相手がされて嫌がる内容ではないか、慎重に考えて行動しましょう。
いろいろなハラスメント
更新日 : 2025年3月17日
ページ番号:000175301
(1)ハラスメントの例
- セクハラ(セクシュアルハラスメント)
労働者の意に反する性的な言動を行い、その対応によって不利益を与えたり、職場環境を不快にさせたりすること。 - パワハラ(パワーハラスメント)
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位な立場を利用して、精神的・身体的な苦痛を与えること。 - マタハラ(マタニティハラスメント)
妊娠・出産・育児などを理由として、解雇などの不利益な取扱いを行ったり、精神的・身体的な苦痛を与えること。 - モラハラ(モラルハラスメント)
倫理的に問題のある言動により、人間の尊厳を傷つけること。 - オワハラ(就活終われハラスメント)
会社が自社に内定した学生に対して、就職活動を終わらせることを強要すること。 - カスハラ(カスタマーハラスメント)
顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為のこと。
(2)事業主がハラスメント防止のために講ずべき措置
事業主は職場におけるハラスメント(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等ハラスメント)を防止するために以下の措置を講じる必要があります。
- ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
- 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
- 相談窓口の設置
- 相談に対する適切な対応
- 事実関係の迅速かつ正確な確認
- 被害者に対する適正な配慮の措置の実施
- 行為者に対する適正な措置の実施
- 再発防止措置の実施
- 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置
(妊娠・出産等に関するハラスメントのみ) - 当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
- 相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発
(3)ハラスメントに悩んでいる方へ
はっきりと拒絶の意思を相手に示すことも大切ですが、自分だけで解決しようとするのではなく、速やかに職場の相談窓口担当者や信頼できる上司に相談し、職場としての対応を求めるようにしましょう。
職場で対応してもらえない場合や、外部の窓口へ相談したい時は、行政機関の相談窓口に相談しましょう。専門の相談員が問題解決の手伝いをしてくれます。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
このページの作成者
産業経済局地域経済振興部雇用・産業人材政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2419 FAX:093-591-2566
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。